| JOTARO on the web | | JOTARO Who? | Chemist JOTARO | |
■JOTARO NOW
Spin-Polarized Donors as a Building Block for Organic Conductive Magnets(スピン分極ドナーを用いた有機磁性導体の構築)
1.はじめに近年、有機導体や有機磁性体に関する研究が進展し、従来は絶縁体・反磁性体であるとされてきた有機物質に対する見方が一新されつつある。これまでに多数の有機超伝導体や強磁性体が報告されており、最近では、磁性・導電性を複合した系への関心が高まっている。その一方で、純有機強磁性体の強磁性相転移温度は、今なお非常に低い温度領域にとどまっているのが現状である。有機物質における伝導電子を介したスピン整列系は、分子間に、より強力な強磁性的相互作用を導入する試みとして提案された。無機物質では、スピン間の相互作用に関して伝導電子が重要な役割を果たしていることが知られており、有機磁性導体の概念は、非常に受け入れやすいものであった。しかし、これを実現するには、まず、導電性を担うドナー部位の酸化により生ずるπカチオンラジカルと、ラジカル部位のスピンとの間に、強磁性的な分子内相互作用を導入することが必要である。このような背景の中で開発された、ドナー部位とラジカル部位を「交差共役系」で連結した分子は、特異な電子構造を有し、一電子酸化により分子内に正の交換相互作用を有するカチオンジラジカルを与えることが判明し、「スピン分極ドナー」と名付けられるようになった。 実際に有機磁性導体を構築しようとする場合、スピン分極ドナーのドナー部位が、有効な導電経路を形成しうることが必要である。本論文では導電経路として、良好な導電性高分子であるポリピロール、および数々の金属的導電体を与えているテトラチアフルバレン(TTF)誘導体の電荷移動錯体やイオンラジカル塩に着目した。その上で、これらを導電経路とする有機磁性導体の構成単位として、一群のピロール系およびTTF系スピン分極ドナーの開発を行った。 これまでに報告されてきたスピン分極ドナーの場合、十分良好な導電経路を形成することが期待できなかった。また、ラジカル部位を有するTTF誘導体において、酸化種が正の分子内交換相互作用を有するものは、これまで知られていなかった。本論文に述べられているスピン分極ドナーは、これらの課題を初めてクリアしたものである。
2.ニトロニルニトロキシドを有するピロールの酸化種におけるスピン相関ピロール系スピン分極ドナーの基本的な枠組みとして、ニトロニルニトロキシド(NN)を組み込んだピロール誘導体が考えられる。この系についての基本的な知見を得るため、ピロール環に対して種々の位置にラジカル部位が置換した誘導体、1-pyrrolylNN (N-NN)、3-pyrrolylNN (β-NN)、4-(1'-pyrrolyl)phenylNN (N-PN)、4-(3'-pyrrolyl)phenylNN (β-PN)を設計・合成した。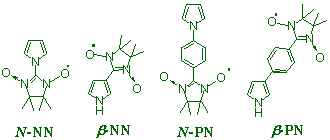 ピロールの分子軌道を考慮すると、ピロール環に直接NNが組み込まれたN-NNとβ-NNは、酸化種がそれぞれ"disjoint"型および"non-disjoint"型のジラジカルに対応するため、酸化種の基底状態が異なると考えられる。実際、β-NNの酸化種は三重項ESRシグナルを示したのに対し、N-NNの酸化種では三重項シグナルが観測されなかった。一方、ピロール環上にパラフェニレンを介してNNが組み込まれたN-PNおよびβ-PNは、いずれも三重項ESRシグナルを与えた。N-NNとN-PNの電子構造の違いは、摂動的分子軌道(PMO)法により説明できる。ここで、ピロール系スピン分極ドナーの電子構造に対し、パラフェニレンが重要な役割を果たしていることが分かった。
3.基底三重項カチオンジラジカルを与えるTTF系スピン分極ドナーの設計TTF骨格にNNを組み込んだ誘導体としては、以前、TTF-NNが報告されている。しかし、その酸化種の基底状態は一重項であった。そこで、酸化種の基底状態が三重項となることを期待し、パラフェニレンを挿入した誘導体TTF-PN、およびその硫黄拡張体であるEMPN、EMTNを設計・合成した。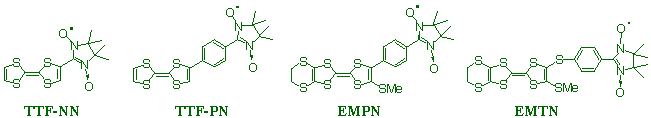 酸化種のESR測定の結果、これらのパラフェニレン挿入型誘導体が、基底状態三重項のカチオンジラジカルを与えることが判明した。EMPNについて観測されたESRスペクトルを図1に示す。
TTF-NNの酸化種は、上述のN-NNの場合とは異なり、disjoint型ではない。TTF骨格とNN部位の間が立体障害のためにねじれ、π共役系が切れた結果、有効な正の交換相互作用が得られなくなったと考えられる。挿入されたパラフェニレンは、この立体障害を緩和し、π共役系を保持する役割を果たしているのであろう。
これらの誘導体について、MOPACを用い、PM3/UHF分子軌道計算を行った。中性の状態では、ドナー部位の軌道とラジカル部位の軌道が、それぞれほぼ独立に存在しており、この計算結果から酸化種の基底状態が三重項となるとは言い切れない。一方、酸化種について計算を行った場合、酸化により生じたπラジカルの軌道(SOMO')が分子全体に広がっており、ラジカル部位の不対電子軌道(SOMO)と空間共有型の軌道となっている(図2)ため、有効な交換相互作用を生じているものと考えられる。 これらのTTF系スピン分極ドナーのうち、単結晶が得られたEMTNについて、電荷移動錯体の調製を行った。錯体の単結晶を得ることはできなかったが、固相混合により得られたF4TCNQとの錯体の磁気測定を行い、イオン性の電荷移動錯体が、比較的安定に存在していることを見出した。
4.縮環TTF系スピン分極ドナーの性質とそのイオンラジカル塩の作成TTF系スピン分極ドナーを用いて有機磁性導体を構築しようとする場合、これらを結晶化させることが必要である。パラフェニレン型誘導体は、酸化種が分子内に強磁性的な相互作用を有していたが、結晶性の面で難点があった。そこで、ドナー部位の平面性向上や分子の対称性の向上を目指し、TTF骨格に縮環した芳香環上にラジカル部位を組み込んだ、ベンゾ誘導体ETBN、チエノ誘導体ETTN、フェニルピロロ誘導体EPPNを設計・合成した。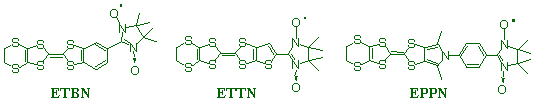
これらの誘導体は期待通り良好な結晶性を示し、X線回折法により、いずれも構造が明らかとなった。ETBNやETTNは、中性状態におけるドナー部位とラジカル部位の間の平面性も比較的良好で、π共役系を通じた相互作用が十分働くと考えられる。また、ETBNの中性結晶は、空間群R3に属し、3回回反軸の周囲に興味ある構造を形成していることが判明した(図3)。このETBN結晶は、磁気測定の結果、正のワイス温度約0.5Kで表される強磁性的分子間相互作用を有していることも明らかとなった。 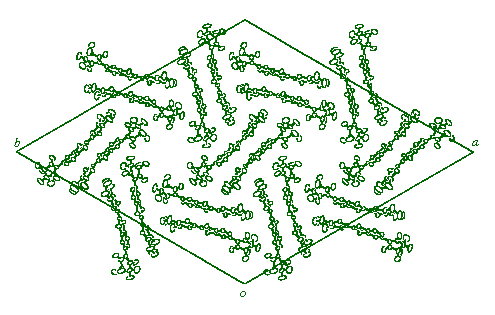 図3 c軸方向から見たETBNの結晶構造 縮環TTF系ドナーラジカルの酸化種が正の分子内交換相互作用を有していることを確認するため、ESR測定を行った。これらのドナーは、良好な結晶性を反映し、酸化種どうし、または酸化種と中性種との会合が起こりやすいため、十分な検討ができなかったが、観測された三重項ESRシグナルは、ほぼ温度の逆数に比例する強度を示した。分子軌道計算の結果と合わせ、縮環TTF系ドナーラジカルがスピン分極ドナーとしての要件を満たしていることが確認された。 これら縮環TTF系ドナーについて、電解結晶化法によるイオンラジカル塩の作成を試みた。n-Bu4N-ClO4を支持電解質として用い、1,1,1-トリクロロエタン(TCE)中でETBNの定電流電解を行ったところ、黒色薄板状のイオンラジカル塩結晶が得られた。その組成は、元素分析の結果から[ETBN]2ClO4[TCE]0.5という2:1塩となっていることが判明した。また、溶媒に10%程度のエタノールやテトラヒドロフラン(THF)を加えた場合、同様の組成の、より良好な結晶が得られたが、X線構造解析には至らなかった。
得られたイオンラジカル塩の吸収スペクトルを観測したところ、電荷移動吸収帯が赤外領域まで現れ、2:1の組成を支持している。またIRスペクトルには、ニトロキシドのN-O伸縮振動に帰属される1350cm-1付近の吸収が観測され、ラジカル部位が保たれていることを示唆している。
2端子法により電気伝導度を測定したところ、この塩は室温付近で約10-2S・cm-1の半導体であり、活性化エネルギーが 0.16 eVであることが分かった。SQUIDによる磁気測定の結果、この塩は常磁性体であり、磁化率の温度依存性はWeiss温度を -5.2 Kとしてほぼ再現できた。Curie定数の値は、式量あたり2個のS=1/2スピンが独立して振る舞っている場合の0.75に近く、各ドナーラジカル分子あたり1個ずつのスピンが存在しているものと判断される。
5.最後に種々のスピン分極ドナーを設計・合成し、有機磁性導体の形が見える段階まで到達した。伝導電子を介したスピン整列系を実現するためには、さらに高伝導性を示す塩の作成が必要ではあるが、この研究によって得られた結果は、そのための道を大きく開いたと言えよう。単離されたイオンラジカル塩は十分安定であり、今後の物性研究の対象として興味深いものである。
[↑目次へ][→審査会で発表した内容] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JOTARO on the web |
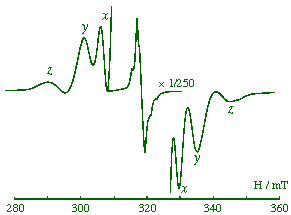
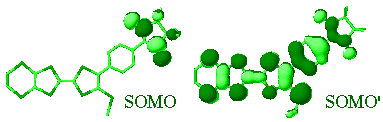
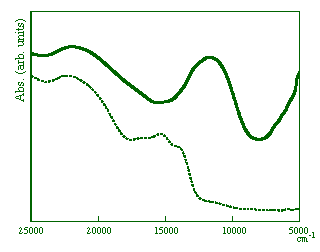
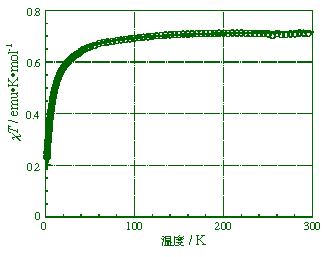
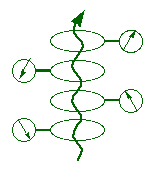 このことから、この塩においては、各ラジカル部位のスピンは保たれている一方、ドナー上のスピンは、磁化率に寄与していないことが示唆される。この塩についてESR測定を行った結果も、この解釈と矛盾しないものであった。ドナー部位にスピンが生じていれば、分子内の強磁性的相互作用が観測されるはずであるが、この塩はバンド絶縁体となってドナー上のスピンが消失し、ラジカル部位のスピンが独立に振る舞っているのだと考えられる。
このことから、この塩においては、各ラジカル部位のスピンは保たれている一方、ドナー上のスピンは、磁化率に寄与していないことが示唆される。この塩についてESR測定を行った結果も、この解釈と矛盾しないものであった。ドナー部位にスピンが生じていれば、分子内の強磁性的相互作用が観測されるはずであるが、この塩はバンド絶縁体となってドナー上のスピンが消失し、ラジカル部位のスピンが独立に振る舞っているのだと考えられる。